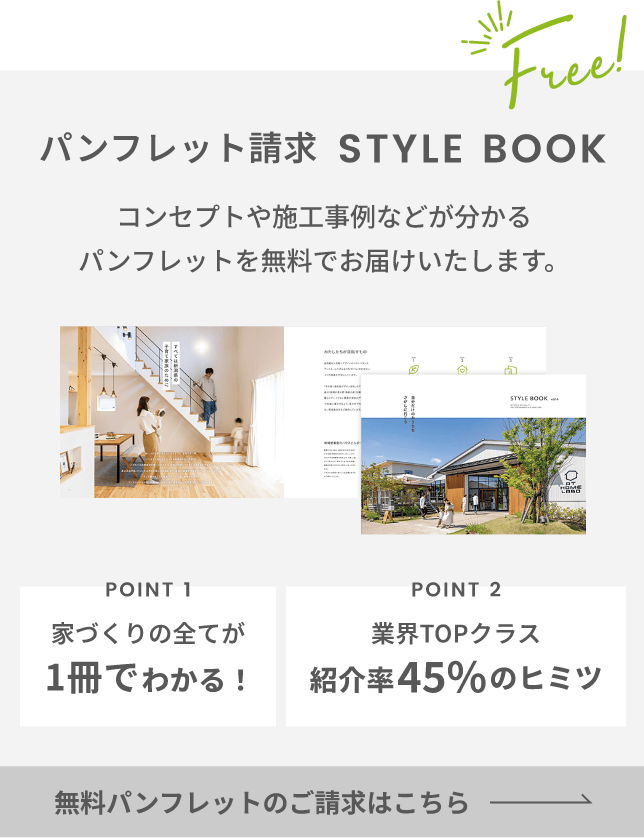ガレージは建ぺい率に含まれる?緩和条件やオーバーを防ぐための対策を紹介

新築や増築でガレージをつくる際には、建ぺい率を考慮する必要があります。
建ぺい率をオーバーすると、理想の間取りが実現できないためです。
居住部分だけでなくガレージにも適用される場合があるため、家を建てる際は計算方法や緩和条件など建ぺい率に関する知識を深めておくことが大切です。
この記事では、ガレージをつくる際の建ぺい率について解説します。
緩和条件や建ぺい率オーバーを防ぐ対策も紹介するので、ガレージの新築・増築をお考えの方は参考にしてください。
ガレージは建ぺい率に含まれる

ガレージは居住部分と同様、建ぺい率に含まれます。
ここでは、以下2つの観点から建ぺい率について解説します。
- 建蔽率(建ぺい率)とは
- 建ぺい率の計算方法
ガレージをつくりたい方は、今後の参考にしてください。
また、新潟県などの雪国でおすすめのガレージが知りたい方は、以下の記事をあわせてチェックしましょう。
【関連記事】雪国にはガレージがおすすめ?おすすめのガレージ3選と価格について解説
建蔽率(建ぺい率)とは
建ぺい率とは敷地に対する建物の割合のことで、建築基準法によって上限が定められています。
土地ごとに建ぺい率が定められている理由は、通風や日照の調整、延焼リスクを減らす目的があるためです。
建ぺい率は各自治体によって決められており、オーバーすると家を建てられません。
つまり、住宅を建てる場合は建ぺい率に基づいて建てなければならないため、理解を深めておくことが大切です。
特に平屋を希望する方は、建ぺい率が問題となることもあります。
建ぺい率を確認せずに土地を購入し、希望する住宅が建てられなかったとならないよう、必ず確認しましょう。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率の計算方法は、以下のとおりです。
|
建ぺい率(%)=(建築面積÷敷地面積)×100 |
建築面積は建坪(※)になるため、床面積を計算する必要はありません。
例えば、300㎡の敷地面積に対して建ぺい率が70%の場合、建築面積は以下の計算方法で算出できます。
300㎡(敷地面積)×70%(建ぺい率)=210㎡
つまり、300㎡の敷地に対して、210㎡の住宅が建築できます。
建ぺい率は簡単に計算できるため、購入したい土地があれば事前に計算しておくとよいでしょう。
なお、建ぺい率は原則、用途地域により細かく分類されています。
各自治体によって建ぺい率は異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
※建築面積の坪数
建ぺい率の緩和対象となるガレージの条件

建ぺい率は地域別に決められていますが、以下の条件を満たす建物では緩和される場合があります。
- 外壁がない部分が連続して4m以上
- 柱間隔が2m以上
- 天井の高さが2.1m以上
- 地階を除く階数が1階
つまり、1階で柱間隔が2m以上あり天井が低すぎない建物は、建築面積の不算入措置と呼ばれる緩和措置が取られるため、建ぺい率を気にする必要がありません。
建ぺい率の緩和対象となるガレージは限られる点についても、あわせて押さえておきましょう。
引用元:国土交通省|平成6年建築基準法の一部を改正する法律等の施行について
建ぺい率に入らないガレージとは

ビルトインガレージは建築面積の中に含まれるため、建ぺい率に影響しません。
ここでは、以下2つの観点からビルトインガレージについて解説します。
- ビルトインガレージの特徴
- ビルトインガレージは容積率に影響あり
ガレージ付きの住宅を検討している方は、参考にしてください。
なお、当社アットホームラボでは、お客様の希望に寄り添った高性能でおしゃれな住宅を提供しています。
新潟県周辺で注文住宅を検討されている方は、「資料請求」からお問い合わせください。
ビルトインガレージの特徴
ビルトインガレージは、建物の1階部分に組み込まれているガレージのことです。
1階すべて、もしくは一部をガレージにする場合もあるため、屋内に駐車スペースを設けられるメリットがあります。
1階部分に組み込まれているビルトインガレージは、建築面積に含まれることから建ぺい率の影響を受けません。
建ぺい率の影響を受けないビルトインガレージの特徴は、以下のとおりです。
- 直射日光が当たらない
- 雨ざらしにならない
- 車の乗り降りが楽になる
- 天候に関係なく、作業できる
- 盗難やいたずらの心配がない
ビルトインガレージは雨ざらしにならないため、乗り降りの楽さだけでなく、車をきれいな状態で保てることもメリットです。
またシャッターをつければ、盗難リスクも減ります。
車やバイクが趣味の方は、天候関係なくビルトインガレージ内で作業できます。
ビルトインガレージは、ライフスタイルに応じて柔軟な空間づくりを実現できる点が魅力です。
ビルトインガレージを取り入れたいものの予算が気になる方は、以下の記事をあわせて参考にしてください。
【関連記事】【失敗しない】注文住宅でコストダウンをするコツと予算オーバーの原因
ビルトインガレージは容積率に影響あり
ビルトインガレージは、建ぺい率には影響しないものの、容積率に影響があります。
容積率とは、敷地面積に対して建築可能な延べ床面積を示す割合です。
建ぺい率同様、容積率にはエリアごとに指定があり、快適な住環境を保つ目的でつくられています。
ビルトインガレージは延べ床面積に含まれるため、容積率に影響します。
容積率の許容範囲内で目一杯居住スペースにはできず、間取りが制限される場合もあるでしょう。
なお、容積率を求める計算式は下記のとおりです。
|
容積率=前面道路幅員×低減係数×100 |
低減係数とは、用途地域によって決められるものです。
容積率には前面道路の幅員が関係するため、正確に求める際は自治体に確認しましょう。
引用元:国土交通省|容積率規制等について
建ぺい率オーバーを防ぐための対策

建ぺい率オーバーにならないための対策は、以下の3つです。
- ガレージを後付けせず事前に設置する
- 必要な広さを把握しておく
- 専門家に相談する
希望の間取りが実現できなかったと後悔しないよう、ポイントを見ていきましょう。
対策①:ガレージを後付けせず事前に設置する
新築物件を建てる際は、図面などを提出する「建築確認申請」があります。
建築確認申請では建築基準法などを守っているか確認されるため、建ぺい率や容積率がオーバーしていれば建築できません。
つまり、住宅を建てる際にガレージを設置しておけば建築確認申請が終わっていることから、違反建築物にはならないのです。
しかし既築物件に後付けする場合、建築確認申請をしない場合もあります。
建ぺい率オーバーに気づかず、売却時に違反建築物としてペナルティが課されてしまう可能性もあるでしょう。
建ぺい率がオーバーしないためには、ガレージを事前に設置することがポイントです。
対策②:必要な広さを把握しておく
建ぺい率のオーバーを防ぐためには、ガレージに必要な広さを事前に把握しておくことが大切です。
車の大きさや台数によって、ガレージに必要な広さは異なります。
車1台につきどのくらいのスペースが必要か理解しておくと、建ぺい率をオーバーしない住宅を建設可能です。
また、車を買い替える可能性も想定する必要があります。
広さの問題により希望の車を購入できなかったと後悔しないためにも、計画を立ててガレージを検討しましょう。
対策③:専門家に相談する
専門家に相談するのも、1つの手です。
建ぺい率や容積率はご自身でも算出できますが、細かな決まりがあったり計算を間違えたりしてしまう可能性があります。
ガレージを後付けする場合もDIYで増設できますが、専門家に相談することがおすすめです。
事前に相談しておくことで、建ぺい率オーバーで違反建築物にならず理想の間取りを実現できます。
アットホームラボでは、設計士と直接話せる無料相談会を開催しております。
ガレージについてもご相談可能なので、気になる方はぜひ「無料相談会」にお越しください。
アットホームラボのガレージハウス施工事例
こちらの家のガレージは木目調の家の外観とマッチしており、ポイントは下以下の2つです。
- 駐車場と家をつなぐ出入口
- 駐車場だけでなく、遊び場としても使える広さ
玄関だけでなく、駐車場からも家に出入りができ、雨の日でも濡れないガレージです。
小さなお子様がいる家庭でも、安心して出かけられます。
車2台分がゆったり停められるスペースを確保しているため、バーベキューなどのアウトドアも楽しめます。
ご家族のライフスタイルに合った使い勝手の良いガレージ付きの施工事例です。
まとめ:ガレージハウスを検討する際は建ぺい率に気をつけよう

ガレージハウスを検討する際には、建ぺい率に注意する必要があります。
建ぺい率には緩和措置などもありますが、違反してしまうとペナルティが課されるため注意が必要です。
理想の住宅を実現できるよう建ぺい率や容積率などは、専門家に相談するのがおすすめです。
当社アットホームラボでは、宅建士や設計士と直接話せる無料相談会を開催しております。
家づくりだけでなくガレージ増設のご相談も可能なため、ガレージ付き住宅を検討中の方は「無料相談会」をお申込みください。
【関連記事】フルリノベーションとは?費用相場・メリット・デメリットを解説
【関連記事】【後悔しない家づくり】家のランニングコストを徹底解説&節約術も紹介
【関連記事】注文住宅を建てる時に決めることリストを紹介!家を建てる時の注意点も
新潟県周辺でガレージ付き高性能住宅の施工事例を見たい方は、WORKSをご覧ください。
この記事の監修 アットホームラボ代表 青木真大(あおきまさひろ) 
二級建築士、二級建築施工管理技士
2006年建築デザイン学部を卒業後、東京と新潟の建築事務所にてデザイン実務を経て、株式会社アオキ住建へ入社。 建築業界で15年間の設計、現場監督経験を経て、住宅事業部の責任者として1,500件以上の新築及び大規模リノベーションに関わる。
新築だけでなくリフォームも承っておりますので、気になる方は是非無料相談会にご参加ください!
ご予約・お問い合わせは、下のCONTACTからお気軽に!